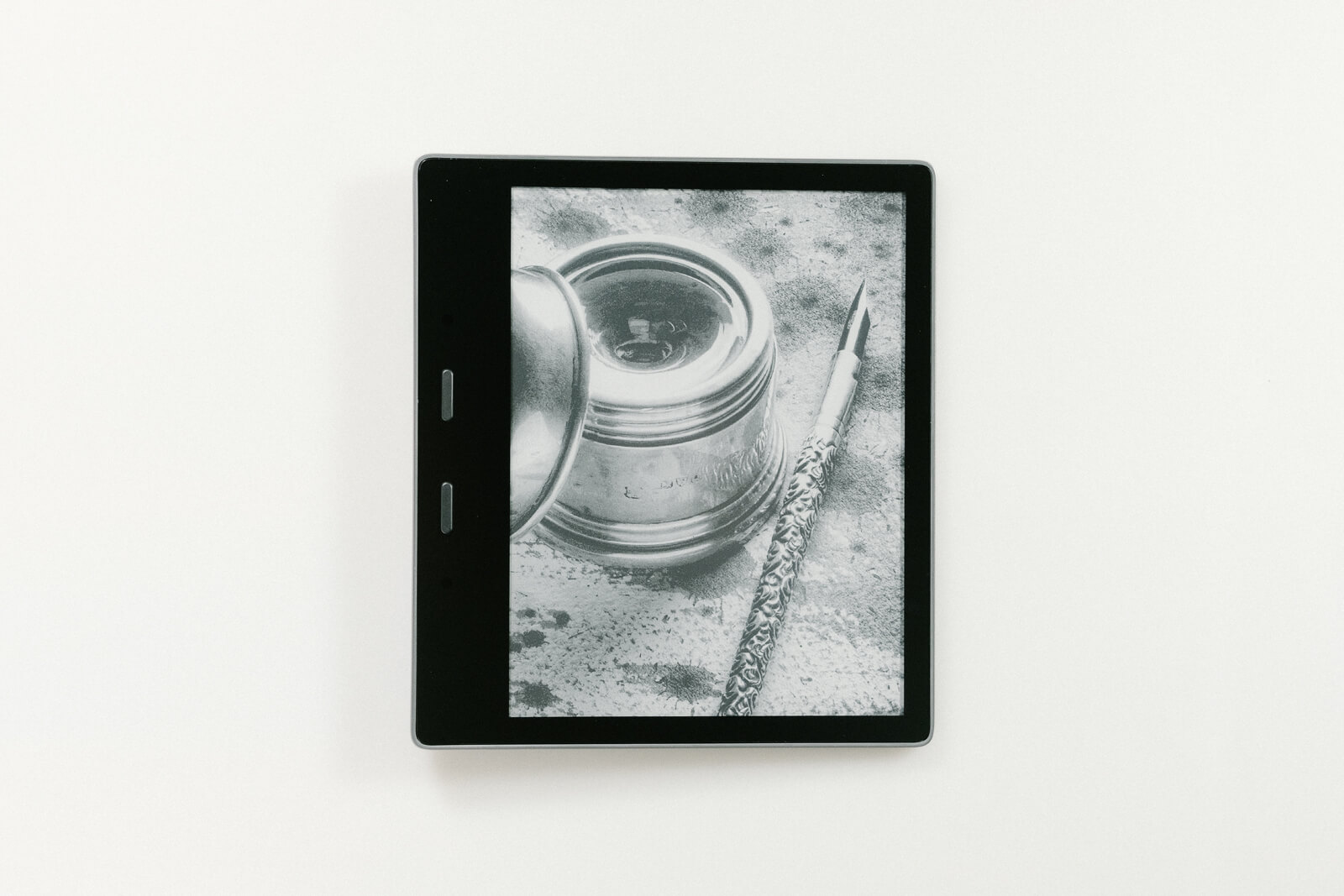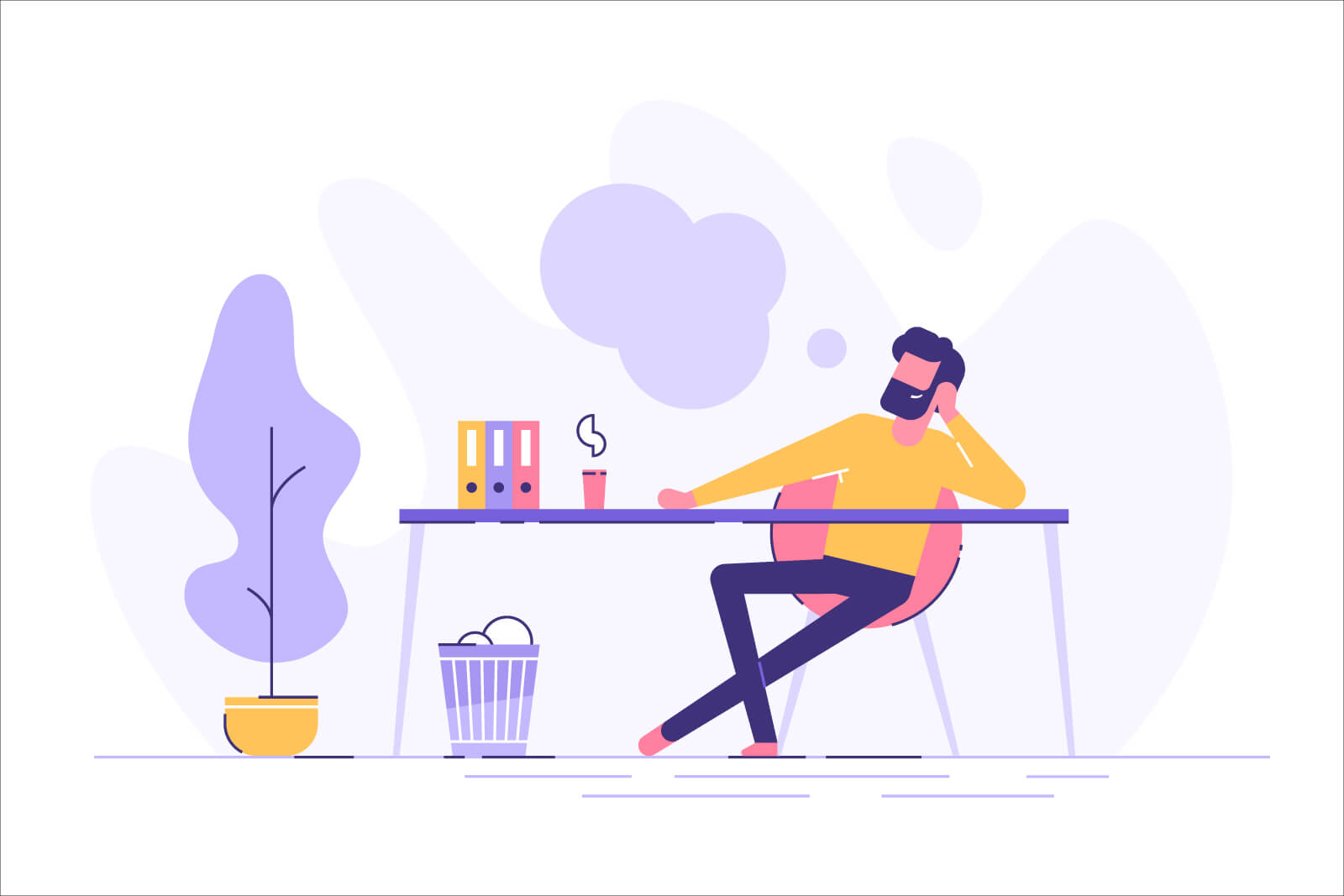ブログの指標の一つが、「平均エンゲージメント滞在時間」です。
平均エンゲージメント滞在時間は、訪問した読者が「どのくらい時間を掛けて文章を読んだか」の指標です。
おもしろいと思ってくれれば最後まで読まれ、滞在時間はのびます。逆につまらないと思えば、すぐに離脱されてしまいます。
平均エンゲージメント滞在時間をのばすには、「読みやすくわかりやすい文章」を書く必要があります。
この記事では、読者へわかりやすく伝えるブログの書き方を解説します。
読みやすいブログとは
読者はどういう文章に読みやすさを感じるでしょうか。答えは簡単です。
その文章が論理的に書かれていれば、読者は「読みやすい」と感じます。
なぜといえば、人間は矛盾を嫌うからです。文章の前後で辻褄が合わなかったり、文脈がつながっていなかったりすると、混乱して納得感が低下します。
論理的な文章を読むと「なるほど、そういうことか」と納得し、おもしろく感じながら読んでくれます。
論理的な文章の書き方
では、論理的な文章を書くにはどうしたら良いか。論理的な文章は、以下の手順を踏むと苦労なく書けます。
1. 問いを立てる
論理的な文章を書くには、まず問いを設定します。
ブログを読む人は、何かしら疑問を解消したいと思っています。
そのため執筆する際は、「読者の疑問の解消」を目的にしなくてはなりません。
読者が疑問に思う「問い」を設定する。これが読みやすい文章を書く第一歩です。
2. 結論を考える
問いを設定したら、文章を書き始める前に結論を考えます。言い換えると結論とは、「その文章で伝えたいメッセージ」です。
3. 理由を「漏れなく重なりなく」考える
結論を考えたら、次に「その結論が導き出される理由」を考えます。
文章内に理由が書いてあると、読者は「なるほど」と納得感を持ちます。
それもただ理由を書けばいいというわけではありません。理由は、「漏れなく・重なりなく」書く必要があります。
納得感のある理由を書く
漏れなく重なりなく理由を書くには、あらゆる角度からの検証が必要です。
入念な検証から生まれた理由を読むことで、「なるほど、確かにこの結論になるな」と説得力が生まれます。
最初にロジックツリーを作る
ここまで、論理的な文章の書き方を説明しました。その流れは、以下3つです。
これらは「ロジックツリー」というツールを使うと、簡単に作成できます。
ロジックツリーとは、以下のように「問い・結論・理由」をビジュアル化したものです。

論理的な文章を書く際は「問い・結論・理由」の順に、ロジックツリーを作成しましょう。ロジックツリーがそのまま文章の構成になります。
「メリット・デメリット」は書きやすい
ブログのよくある記事に、「〇〇のメリット・デメリット」がありますね。レビュー記事で、この形式のタイトルを見たことがあると思います。
なぜこの形がよく使われるか、理由は2つです。
- 論理的な文章にしやすいから
- 読者にとって読みやすい文章になるから
メリットとデメリットを書き出せば、理由をごく簡単に「漏れなく重なりなく」書けます。
メリットとデメリットにわけて論理的に書かれるため、「なるほど、そういうことか」と納得感を生みやすいのです。
ロジックツリーの例
では「〇〇のメリット・デメリット」を、ロジックツリーで表してみます。

タイトルの「〇〇のメリット・デメリット」が「問い」です。読者は「この製品のメリットとデメリットは何だろう?」と疑問を持ってこの文章を読みます。
「問い」のすぐ後に「結論」が来て、その下に「理由」であるメリットとデメリットが来ます。
メリットとデメリットを漏れなく書けば、論理的な文章が自然にできあがります。
ロジックツリーの作成ツール
ロジックツリーは、ツールを使うと簡単に作成できます。無料で使えるツールを2つ紹介します。
- XMind
- Dynalist
XMind
XMindは、文章の構造を視覚的に作成できます。図の形式をいくつか選ぶことができ、ロジックツリー用のフォーマットもあります。
Dynalist
Dynalistは、文章のアウトラインを作るためのツールです。こちらはロジックツリーではなく、形式は箇条書きです。
文章の構成は2パターンある
ではここから、実際に文章を書く際のパターンを紹介します。パターンを覚えると、文章を書く際の苦労がかなり軽減されます。
ウェブ上の多くの文章は、以下の流れで構成されています。
【パターン1 結論を先に書く】
問い → 結論 → 理由1 → 理由2 → 理由3… → まとめ
「問い」が来て、次に問いに対する「結論」が来ます。その結論にいたる「理由」が来て、最後に「まとめ」が来ます。
先ほどのロジックツリーと同じ流れですね。
結論が問いのすぐ後に来る理由は、その方が読みやすい文章になるからです。結論がわかった上で文章を読んだほうが、すんなり頭に入ってきます。
結論が最後に来るパターン
一方、あえて結論を最後に持ってくるパターンもあります。
【パターン2 結論を最後に書く】
問い → 理由1 → 理由2 → 理由3… → 結論 → まとめ
結論を最後に書くと、よりストーリー性のある文章になります。情報よりストーリー性を重視したい場合、結論を最後に持ってくると良いです。
ただし結論を最後にすると、特に無料で読めるウェブの場合は離脱される可能性が高まります。
「この文章はおもしろいから、最後まで読んでくれる」と自信のある場合だけにしておいたほうが無難です。
参考になる本の紹介
論理的な文章を書く際に、参考になる書籍を2冊紹介します。この2冊を読むだけでも、かなり文章が書きやすくなると思います。
- 『理科系の作文技術』
- 『ロジカル・ライティング』
『理科系の作文技術』
特に論文や報告書などは、事実を明瞭な文体で書く必要があります。この本では、文章を明瞭に作成する必要性とその方法が書いてあります。
『ロジカル・ライティング』
タイトル通りロジカル・シンキングを用い、論理的な文章の書き方を指南してくれます。
ロジックツリーや漏れなく重なりなく(MECE)についても、わかりやすく書いてあります。
まとめ
以上、読者へわかりやすく伝えるブログの書き方の解説でした。
読みやすい文章というと「漢字と平仮名の割合」「語尾を単調にしない」など、細かいテクニックが注目されがちです。
もちろんそれらも大切ですが、いくら漢字と平仮名の割合が良くても辻褄の合わない文章はすぐに離脱されます。
以下、3つの順序に沿って、論理的な文章を書いてみてください。
論理的な書き方に慣れると、ロジックツリーなしで書けるようになりますよ。
この記事の冒頭で紹介した「ブログの平均エンゲージメント滞在時間」については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。