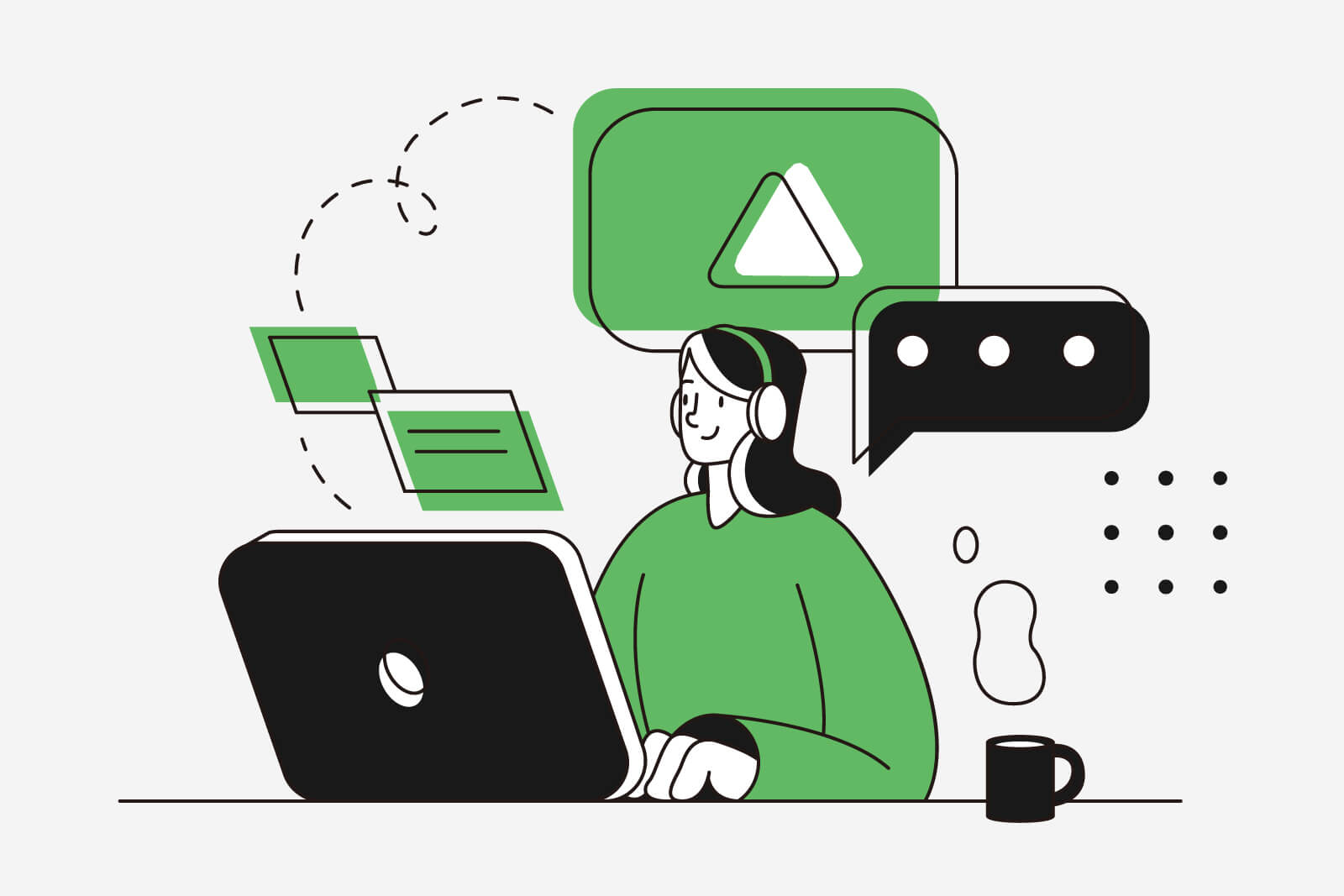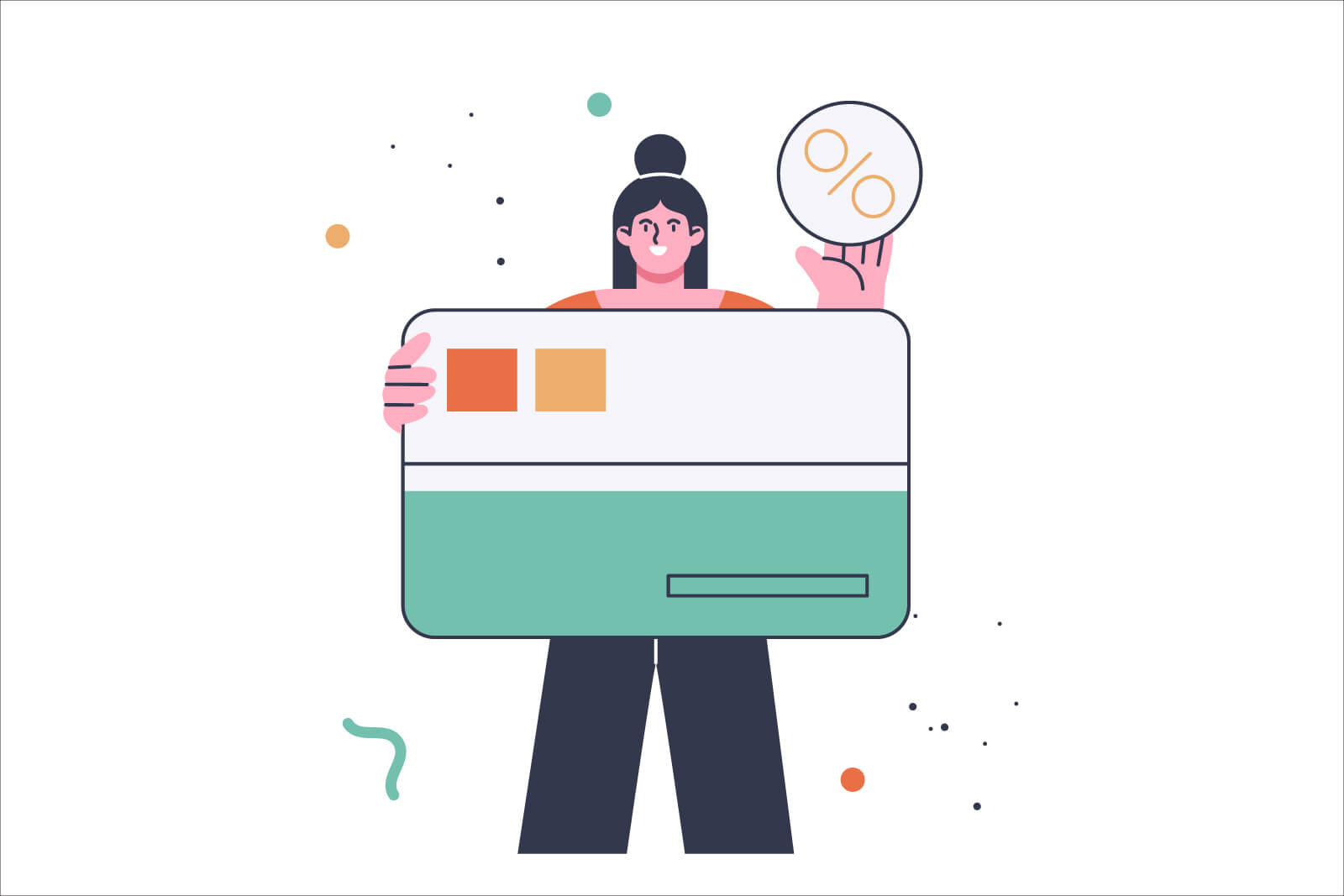スマホはあまりに便利なので、つい触るのが癖になります。
歩きながらもスマホ、誰かと一緒にいてもスマホ。まるでスマホに人間が操られているようです。
「スマホばかり見るのは、良くないのではないか…」と多くの人が薄々、気づいているはず。
この記事では、スマホを見なくする方法を解説します。
スマホ見る時間を減らすには
いまやスマホは、1人1台以上を持つ時代です。無意識レベルで、何度もスマホを見ているひとは多いでしょう。
ここで質問です。皆さんは、一日に何回スマホを見ていますか?
「そんなの数えたことないからわからない」と思うかもしれませんが、スマホには持ち上げた回数を確認する方法があります。
例えばiPhoneの場合は、以下でわかります。
【スマホを持ち上げた回数の確認】
設定 > スクリーンタイム > すべてのアプリとWebサイトのアクティビティを確認する > 持ち上げ
スマホを持ち上げる回数は平均52回
株式会社 PR TIMESが2021年3月に実施した調査には、1300人のiPhoneユーザーの「1日に持ち上げた回数の平均」が記載されています。
それによると、iPhoneを1日に持ち上げた平均回数は52回でした。
1時間に3回、スマホを起動している
一日24時間から睡眠の8時間を引くと、活動は16時間。つまり人は活動中に、1時間に3回ほどスマホを持ち上げていることになります。
この数字を踏まえた上で、自分のスクリーンタイムを確認してみてください。平均の52回を大きく越えているなら、スマホ依存の認識で良いと思います。
スマホ依存が引き起こす5つの問題
スマホを何回も持ち上げているとしても、「それで?スマホ依存の何が悪いの?」と思うかもしれません。
確かにスマホはアルコールやギャンブルなどに比べると、特に害がなさそうです。
スマホ依存はすぐに影響あるわけではないですが、長期的に心身へ悪影響を及ぼします。具体的には以下の5点です。
1. 食事
スマホはエンタメ消費に優れた端末です。ゲームや動画、SNSに夢中になると、食事中もスマホを見るようになります。
食事よりもスマホを優先する結果、ジャンクフードや軽食が多くなり栄養バランスが崩れます。
食事は人間を形成する基本です。スマホ依存は、健やかに生活する基本を脅かします。
2. 睡眠
スマホに夢中になると、深夜まで触るようになります。
寝る直前までスマホの画面を見て、寝るときには枕元に置くようになる。
直前までブルーライトを見ることで寝つきが悪くなり、近くにスマホがあることでリラックスできない。これでは質の高い睡眠をとれません。
その結果、睡眠不足になり、日中は万全な状態でパフォーマンスを発揮できなくなります。
3. 体調
小さな画面のスマホは、体にとってよくありません。うつむいて見続ければ目が悪くなるし、眼精疲労で疲労感が抜けにくくなります。
またストレートネックで、肩こりや頭痛も引き起こします。姿勢が悪くなると、見た目的にも良くありません。
4. 人間関係
誰かといるときもスマホを見ていれば、コミュニケーションに支障をきたします。
会話中にスマホをテーブルに置くだけで、意識がそちらに取られることが研究でわかっています。
想像してみてください。久しぶりに会った友達がテーブルに向かい合わせに座った途端、スマホの画面を見始めたらどんな気持ちがしますか?
多くの人が「目の前にいる自分よりも、スマホの方を優先するんだ」と、寂しい気分になると思います。
スマホと人間関係のどちらが大切か考えるまでもないですが、わかっていても依存状態になるとつい画面を見てしまうのです。
5. 時間の浪費
スマホの小さな画面には、ゲームや動画、SNSなど、魅力的なコンテンツが無限にあります。
コンテンツの製作会社は一秒でも長く画面を見させるためのあらゆる施策を行うため、無自覚に使っているとどんどん時間を取られます。
いくらおもしろい時間を過ごせたと思っても、動画やゲームなどコンテンツを消費するだけでは自己成長できません。
人生の限りある貴重な時間が、スマホ依存によって失われます。
悪影響を認識しておく
他にもスマホをそばに置くだけで学力が低下したり、うつを引き起こしたりと悪影響は数しれず。
『スマホ脳』を読むと、恐ろしさを知ることができます。
もちろん誰もがこういった症状におちいるわけでないですが、「スマホ依存は、最悪こういった状態を引き起こす」と知っておくのは大事です。
スマホはあまりに便利だからこそ、我々の体と精神、周囲との関係を破壊しえる危険なものでもあるのです。
スマホの使用方法は3種類に分けられる
ではスマホ依存にならないために、どうしたらよいか。
まずはスマホの使用方法を分類してみましょう。大きく以下3つに分けられます。
1. 道具として使用
スマホを道具として使用する分には、いくら使っても問題ありません。道具としてのスマホ利用には、以下があります。
- メモ帳
- メールやメッセ
- 音楽
- カメラ
- カレンダー
- 電子マネー
- マップ
- 家計簿
- 歩数の計測など健康管理
カメラやメモを頻繁に使っても、「カメラを起動しないと落ち着かない」「メモを使った後、またすぐ起動したくなる」なんてならないですよね。
使用するだけの明確な目的があり、成果を効率的に出すための道具としてスマホを使うなら、依存状態にはおちいりません。
2. 暇つぶしで使用
問題は暇つぶしで使用する場合です。暇つぶしのスマホ利用には、以下があります。
- SNS
- 動画
- ゲーム
スマホのスクリーンタイムを確認してみてください。使用時間の多くをこれらが占めているなら、依存状態の可能性が高いです。
「仕事でSNS担当になった」などは例外ですが、「SNS・動画・ゲーム」は、本来、必要性のない行動です。あくまで暇つぶしにすぎません。
暇つぶしなのに、しょっちゅうこれらのアプリを開く。その状態は要注意です。
プラットフォームは、あなたの生活など一切考慮しない
SNSやゲームを製作している会社は、ユーザーの生活など一切、配慮しません。
彼らにとっては、むしろスマホ依存にしたほうが儲かって都合が良いのです。たとえ、ユーザーの生活が破壊されたとしても。
「SNS・動画・ゲーム」は、いずれもユーザーを依存状態にさせるための仕組みが盛り込まれています。
そのことを自覚しないと、簡単に依存状態におちいります。
3. そのどちらにも当てはまるもの
最後に気をつけたほうが良いのは、「道具としても暇つぶしとしても当てはまるもの」です。
例えば、以下のアプリがあります。
- メッセ(LINE)
- ニュース
- ショッピング
これらを、明確な目的があって使うならよいです。しかし目的もないのに「つい開いてしまう」なら要注意です。
スマホ依存から脱する5つの方法
ではどうすれば、スマホ依存から抜け出せるでしょうか。
スマホをポケットに入れた状態で「見るのを控えよう」と思っても、それは無理な話です。意志の力は有限なので、脳が疲れると制御できなくなります。
見ない努力をするのではなく、見ない仕組みを作りましょう。
具体的には、以下5つの方法があります。
1. 通知を切る
スマホは起動していなくても、ロック画面に通知がきます。
通知がきたからとスマホを起動すれば、ついでにSNSを一通りながめ、ニュースサイトをチェックして…と、気がつけば5分10分と時間を取られます。
ランダムに来る通知は、脳にドーパミンと呼ばれる快楽物質をもたらします。スマホが気になってしまうのは、脳が快楽を覚えてしまっているからです。
通知はカレンダーやリマインダーなど生活に必要なものだけにし、残りはメールやメッセを含めて全部切っておきましょう。
2. 外出時はスマホをバッグに入れる
ズボンや上着のポケットにスマホを入れると、その存在を常に感じます。スマホは視界に入るだけでなく、存在に触れるだけで起動したくなります。
外出時にはスマホをバッグに入れ、存在感を消すようにしたほうが良いです。
3. 家の中でスマホ置き場を作る
家ではスマホ置き場を作り、そこだけに置くようにします。
スマホ置き場に適しているのは、玄関やキッチンなど目につかない場所です。家に帰ったらスマホをその場所に置いて、あとは触れないようにします。
スマホを見る癖をなくす
スマホ置き場を作りそこから離れれば、存在が気になりません。メッセなどを確認するときは、スマホ置き場へわざわざ行くようにします。
この習慣を続ければ、「ついスマホを見る癖」がなくなります。
4. 就寝時は別の部屋に置く
特に寝るときには、スマホを別の部屋に置いたほうが良いです。
寝る前にディスプレイを見ればブルーライトで目がさえるし、脳が興奮し寝付きも悪くなります。枕元にスマホがあると、存在が気になり睡眠の質が低下します。
寝室にスマホを持ちこんで、良いことは何ひとつないと断言できます。
5. スマホを家の中に持ち込まない
スマホは視界にあるだけで、気になります。ならばそもそも、家に持ち込まなければ良いのです。
車で通勤しているなら、家へ入る前にダッシュボードへしまってはどうでしょうか。
スマホが家の中になければ気にならないし、チェックしたくても、さすがに車まで行く気にはなりません。
依存しない仕組みを作る
そのほかの対策に、SNSアプリを削除したり、ロック画面解除のパスワードを長くしたりする方法もあります。しかし、それらはあまり効果がないです。
なぜならスマホが目に入る場所にあれば、そのたび「スマホを気にしない」と意志の力を消費するからです。
1日に使える意志の力には、限りがあります。
意志の力を使い切った夜には、結局またスマホを見たくてアプリをインストールしたり、パスワードを元に戻したりする可能性が高いです。
スマホが目に入らないようにする
依存から脱するのに一番よいのは、「スマホを見ないようにする」ではなく、「スマホを見れない環境を作る」ことです。
スマホをつい起動するのは、あなたのそばにあるからです。そばにあるだけで、無自覚につい触ってしまいます。意識から消すため、視界に入らないようにするのです。
スマホはあくまでも、生活を便利にするツール。用もないのについ手にする癖は、仕組みを使ってやめていきましょう。
まとめ
以上、スマホ依存から脱する方法を解説しました。紹介した方法は以下5つです。
iPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズは、自分の子どもに対しデジタルスクリーンを見ることを厳しく制限していました。
マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは、子どもが14歳までスマホを与えなかったといいます。
革新的なデジタル製品を生み出したひとたちは、スマホの危険性を十分にわかっていたのです。スマホの怖さを理解した上で、適切な距離で付き合っていきましょう。
スマホで特に時間を取られるのは、YouTubeです。
実際にぼく自身が感じた、YouTubeをやめて感じたメリットを以下にまとめました。合わせて参考にしてみてください。