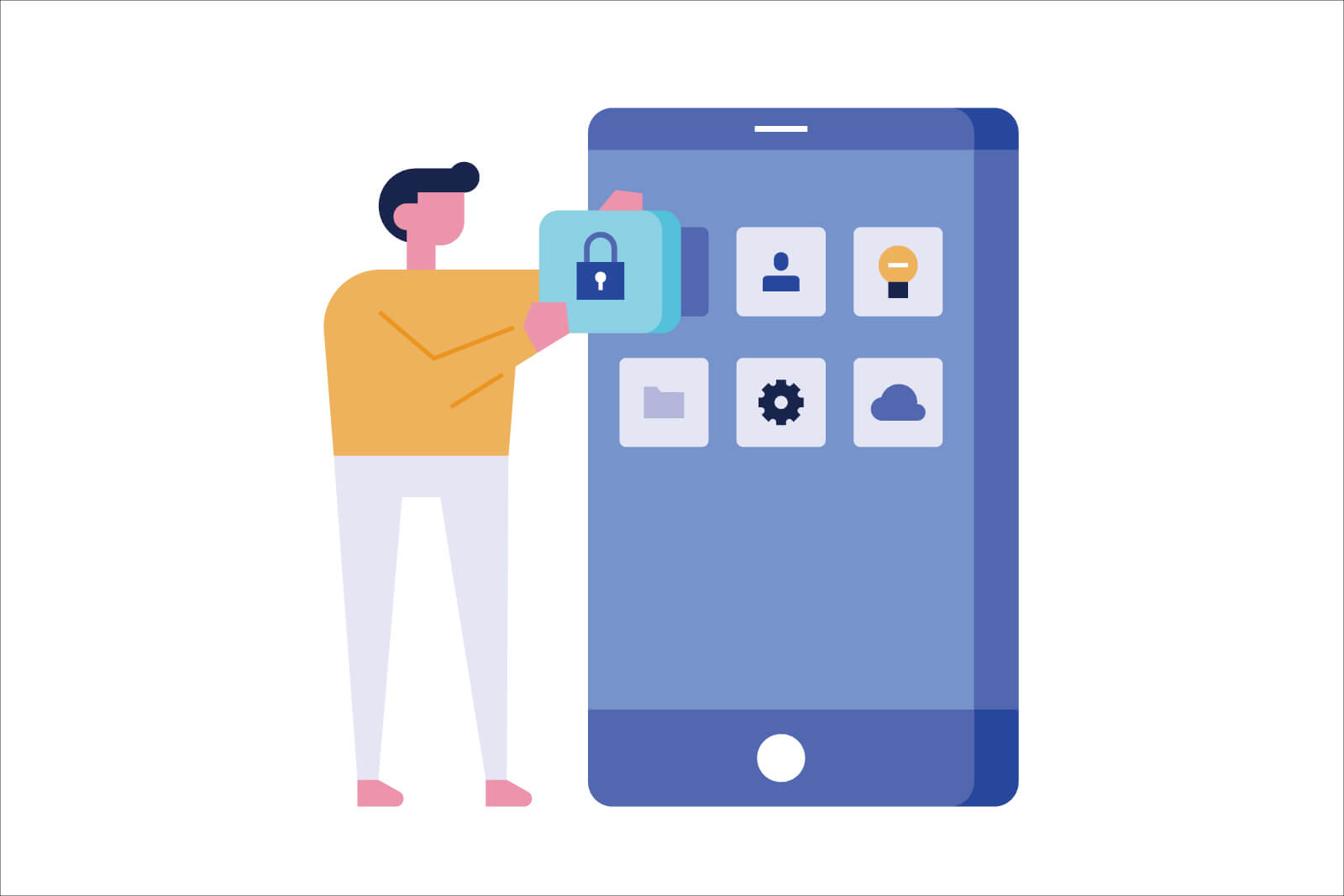常に何かしら不安がありませんか。
日本人は不安を感じやすい民族です。順調にいっていても、何かしら落ち着かない部分があったりします。
そんなときは、瞑想を試してみてください。瞑想すると心が落ち着き、リラックスできます。
この記事では、瞑想のやり方と効果を解説します。
不安を感じやすい日本人
日本人は他の国の人に比べ、「不安を感じやすい」といわれています。
人間の体には、精神に影響を与える様々な物質が入っています。そのなかで不安感を抑える物質が、セロトニンです。
セロトニンには「SS型・SL型・LL型」の3種類の組み合わせがあります。
- SS型
- SL型
- LL型
このうちSS型は、不安感を抑えるセロトニンの量が最も少ないです。日本人はこのSS型が、割合的に最も多いのです。
つまり日本人の多くは、もともと不安を感じやすい性質といえます。
日本人は不安を感じやすい民族なのです。「もっと多くの財産があれば幸せなのに」と思う人が多いのは、日本人が強欲だからではなく、心配症だからなのでしょう。
「自分は不幸」と思う日本人がやたら多い不思議 東洋経済オンラインより
「そういう性質ならしょうがない」と割り切れるにせよ、「気がつくと、不安なことを考えてしまう」のはつらいものがありますね。
スマホの見過ぎでうつになる
またスマホ依存症になると、うつを発症する恐れがあるといわれています。スマホ依存を自覚するなら、意識的に距離を取ったほうがよいです。
スマホ依存から脱却する方法は、以下に書いています。合わせて参考にしてみてください。
>> スマホ見る時間を減らすには【依存状態から自由を取り戻す】
日本人が持つもともとの性質に加え、現代はスマホ依存で不安に拍車をかけているのです。
瞑想を行なって、余計な不安感は軽減させていきましょう。
瞑想には3つの種類がある
ひと口に瞑想といっても、大きく3種類あります。
- サマタ瞑想
- ヴィパッサナー瞑想
- マインドフルネス瞑想
瞑想はもともと、仏教で始まりました。
そこから宗教的な要素を排し、リラックスや集中力アップなど良い効果だけを狙い広まったのが3のマインドフルネス瞑想です。
この記事では、マインドフルネス瞑想のやり方を取り上げます。
瞑想のやり方
マインドフルネス瞑想(以下瞑想)のやり方は、とても簡単です。基本的には座って目を閉じ、腹式呼吸をするだけです。
座り方
座り方は、いちばん楽な体勢で大丈夫です(椅子でもOK)。
一般的に広く知られているのは、半跏趺坐(はんかふざ)です。
半跏趺坐(はんかふざ)とは、あぐらをして、片方のつま先をもう片方のふくらはぎ辺りに乗せる座り方です。
座ったら呼吸が深くなるように、背筋を伸ばします。両手をそれぞれ両膝辺りに置き、親指と人差指で輪っかを作ります。
これで基本姿勢が完了です。
呼吸は吸ったときにお腹を膨らませ、吐くときに縮ませる「腹式呼吸」で行います。
目を閉じて鼻で息を吸い、口からはき出します。そうして何も考えず、10〜15分くらい瞑想します。
「何も考えない」のが難しい
これだけ聞くと、簡単に思うかもしれません。しかし実際やってみるとわかりますが、最初はとても難しく感じると思います。
何が難しいか。この「何も考えない」が、ものすごく難しいのです。
脳は24時間、休まない
人間の脳は、とりとめない思考を休むことなく続けます。
「雨が降ってて嫌だな」
「この間、嫌味をいわれたけど、どういうつもりなんだろう」
「冷蔵庫のヨーグルトがもうないかも」
など、キリがありません。
眠っているときも、脳は記憶の整理のために働いています。まさに休むことなく24時間働いているのが、脳という機関です。
瞑想をする目的は2つ
脳がこれだけ働き続ければ、「瞑想するから思考を停止しよう」と急に思っても、難しいのは当たり前です。だからこそ瞑想はやる価値があります。
瞑想の目的は、以下2つです。
- 脳を休ませるため
- 「普段から自分は、これほど思考し続けている」と気づくため
瞑想していると、脳の働きを客観視できます。「脳は放っておくと勝手に思考し、ネガティブになるのだな」と気付けます。
ネガティブな思考は、それが必要だからやっているのではありません。脳の思考の癖が、そうさせているのです。
感情の揺れを瞑想で少なくする
瞑想をしていると、「また思考が始まった」と脳の癖を客観視できます。すると普段の生活でも、自分の思考を客観的に見られるようになります。
わけもなく不安になったときや、人から何かを言われショックを受けたとき。色々な要因で、ぼくたちの感情は大きく動きます。
普段から瞑想を習慣にしていると、そういったとき「自分は今、感情が大きく揺れている」と気づき、感情の揺れを少なくできます。
瞑想には、リラックスや集中力アップの効果があります。その大きな理由のひとつは、この「思考の客観視」なのです。
「何も考えない」2つのテクニック
といっても、瞑想をやってすぐ「何も考えない状態」へは持っていけません。前述の通り、脳は放っておくとすぐに思考を始めます。
何も考えない状態に保つテクニックが、2つあります。
1. 呼吸に意識を向ける
瞑想中は腹式呼吸で鼻で深く息を吸い、口からゆっくりとはき出します。そのとき、呼吸に意識を向けるようにしてみてください。
呼吸する際に鼻から空気が入り、口から出ていくのを感じます。その感覚に、意識を向けるのです。
呼吸に意識を集中することで、余計な思考が入りにくくなります。
2. 「あとで」と思考を追いやる
もう一つの方法は、何か思考が出てきたら「あとで」と脳へ告げる方法です。
「あとで」と告げると、思考はいったん意識からいなくなります。
しかし思考は、このくらいで諦めたりしません。ひとつの思考がなくなっても、また新しい思考が出てきて瞑想の邪魔をします。
すると再び「あとで」と告げて、その思考を追い出す。これを繰り返すと思考が尽きて、新しい考えが浮かばなくなります。
瞑想の効果
こうして瞑想を習慣すると、不安に思ったりネガティブな方向へ考える傾向が減っていきます。
もちろんなくなりはしませんが、そういった考えが湧き出たとしても、「これは問題解決が必要なものか、それとも思考の癖なのか」と客観視できます。
感情に振り回されることが減るため、よりリラックスして生活できるようになると思います。
集中して瞑想できないとき
といっても、ときには重大なトラブルに巻き込まれ、心が休まらないときもあるでしょう。
ぼくの経験上、そんなときに瞑想をやろうとしても無駄です。
目を閉じて呼吸に集中しようとしても、解決せねばならない不安要素が頭から離れず、瞑想に集中できないのです。
瞑想に集中できないと、「やはりこの問題は、早急に解決しなければならないのだ」と精神的に追い込まれるため逆効果にすらなります。
自然を見ながら、歩く
そんなときは瞑想をせず、短時間でもいいので散歩をおすすめします。川沿いの道や公園など、木々や水の流れを見ながら、同じペースでただ歩くのです。
もちろんそうしていても不安はあふれてきますが、木々や水を見つめながら散歩すると、不思議と気持ちが落ち着いてきます。
トラブルがあって心が落ち着かないときは、瞑想をせず、自然の中で散歩してみましょう。
まとめ
以上、瞑想のやり方と効果を紹介しました。
常に不安感のある日本人にとって、瞑想は効果的です。毎日、ほんの10分取り入れるだけで、リラックス効果があります。
瞑想は、いつでも一人きりでできるのも利点です。生活に瞑想を取り入れて、健やかな日々を送っていきましょう。